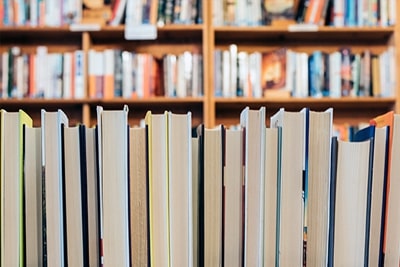1.プロローグ
現在は、母の母国である日本で主に生活していますが、私の父は、ギリシャの外交官であったため、幼少期は、実に多くの国で生活しました。
そのため、ギリシャ語、日本語、英語はもちろんのこと、仏語、独語については、文学作品を読める程度の語学力を持っています。
ヨーロッパという地域は、ギリシャ/ローマ(ラテン語)の文化をベイスとし、その上にキリスト教が乗っているという、ある一つのまとまった歴史的背景を持っています。
それに加えて、古代から各地域の文化の名残りや、イスラム文化の影響などが入り混じり、とても複雑な文化・言語体系を持っています。
ほぼ単一の民族(琉球やアイヌなどを除く)のほぼ単一の文化(中国や朝鮮半島の文化の影響も大きい)を持つ日本とはとても対照的なのがヨーロッパという地域です。
こうしたヨーロッパの多様な文化の違いを知ることは、日本人にとって、“グローバル化"時代を生き抜く上で、必要不可欠なのではないでしょうか。
その代表的な国が、スイスという永世中立国です。スイスは、独自の文学を持った一方、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語が公用語として使用されています。また、国名は、ラテン語でも“Confoederatio Helvetica"と決められています。
私自身としては、権威的文学賞というのものは本来はあまり好みではありません。
特に、日本からの注目の高い近年のノーベル文学賞は、あまりにも政治的なので、どうかと思っています。しかしながら、文学賞の受賞作品にもとても素晴らしいモノがあるので、今回は、ノーベル文学賞と、イギリスの権威ある文学賞であるブッカー賞の受賞者の作品の中から、私の人生に影響を与えた小説を紹介していきます。
2.ノーベル文学賞とは
スウェーデンの学士院である「スウェーデン・アカデミー」が選考委員会を務める文学賞です。1901年より、文学の分野の中で「理想的な方向性の」創作をしてきた人物(作品でなく)が表彰の対象としてきました。今や世界で最も権威ある文学賞とされる一方で、スウェーデン人から構成される選考委員会のセレクションがヨーロッパの作家に偏っていることや、彼らとは異なる政治思想を持った作家をなかなか表彰しないことなど、批判的な意見も多いのが現状です。2018年には、#MeToo運動を背景に、会員の夫であった作家のセクハラ疑惑が報道され、その作家が更に受賞者の名前を事前に漏洩していた事実も判明しました。この騒動の結果、2018年の選考を見送ることを発表しました。
3.ヘルマン・ヘッセ (ドイツ/スイス)
20世紀前半のドイツを代表する小説家、詩人です。アイデンティティの模索や自己実現、精神的な遍歴(へんれき)(今でいう“スピリチュアリティ")をテーマとして様々な作品を発表しました。1946年にノーベル文学賞を受賞し、それをきっかけに、徐々に世界的な評価が広まっていきました。特にアメリカでは、1960年代のカウンターカルチャー(いわゆる“ヒッピー")運動によって、若者の間でも認識されるようになりました。
●『車輪の下』(1905年)
詩人になりたい、だけど勉強に専念しなきゃいけない・・・ヘッセはティーネイジャーの頃、このような気持ちにさいなまれるうちに、不眠症とノイローゼを患うようになりました。神学校から脱走し、その後自殺未遂を図り、神経科病院に入院しました。これらの経験が自伝的長編小説『車輪の下』の元となっています。人間としての成長をないがしろにして、勉強ばかりに打ち込むことを求める現代の大人社会に疑問を投げかけています。睡眠を削って勉強に明け暮れる日本の受験生には、どうせ睡眠を削るなら、その時間を使ってこの本を読んでもらいたいものです。
4.アンドレ・ジッド (フランス)
20世紀を代表するフランスの作家であるジッドの作品には、社会の通念によって決められた“狭い"枠組みの中で、葛藤している彼自身の姿が反映されています。また、同性愛を“病"として捉えていた当時のフランス社会の中で、作品を通して自身の性的指向と向き合い、1920年代には同性愛を擁護するエッセイ集を発表し、自伝で自身の性に対する目覚めも告白しています。1947年にノーベル文学賞を受賞しました。
●『狭き門』(1909年)
主人公の少年がキリスト教的禁欲主義に憧れる従姉に恋心を抱き、また彼女の妹(いもうと)が逆に主人公に好意を抱き、その三角関係の中での様々な遠慮や心の葛藤、自己犠牲を描いた作品です。題名は新約聖書にあるイエス・キリストの言葉に由来しており、救いに至る道にある“狭き門"は、すなわち愛し合う二人が通るには狭すぎると捉えた従姉は、主人公との恋を諦めます。ジッドは、このような“狭い"道徳概念を批判しています。
5.ガブリエル・ガルシア=マルケス (コロンビア)
ガルシア=マルケスは、“魔術的リアリズム"の旗手として様々な作品を残したコロンビアの小説家です。日常の平凡な風景の中に非日常的な魔法や幻想的な要素を織り込んだ作風は、当時のラテン・アメリカ文学の一つの特徴でした。ガルシア=マルケスは1982年にノーベル文学賞を受賞しましたが、『ラテン・アメリカの孤独』と題した受賞演説の中で、ヨーロッパによる中南米の植民地化などラテン・アメリカの暗い歴史について語りました。その中で、より良い生活を求めて努力をしているにもかかわらず、未だにヨーロッパを中心とした先進国からは見下され続けているという意味で、ラテン・アメリカは今もなお“孤立"していることを訴えました。
●『百年の孤独』(1967年)
コロンビアの架空の村“マコンド"を創成したブエンディア一族の祖とその子孫が生きる栄枯盛衰の100年を描いた本作は、ガルシア=マルケスの最高傑作とされています。ラテン・アメリカ文学のブームの引き金となり、数々の「世界文学の歴代名作」のリストにも選ばれています。中米からの移民集団“キャラバン"に対するアメリカ合州国の対応が注目されている中、現在、最も読むべき1冊なのかもしれません。
6.J・M・クッツェー (南アフリカ)
南アフリカの小説家、言語学者であるクッツェーは、実験的かつ寓意的な作風を通して、植民地の現実とそれがもたらす様々な影響を主なテーマとして取り上げてきました。2003年にノーベル文学賞を受賞しました。英国の最高の文学賞である「ブッカー賞」を2度受賞しています。
●『マイケル・K』(1983年)
アパルトヘイト時代の南アフリカを舞台に、架空の内戦を生き抜こうとする、口唇裂を持つ主人公のマイケルの物語です。マイケルは病んだ母親を車椅子に乗せて、ケープ・タウンから彼女が生まれた土地までの旅を試みます。その道中で、マイケルはマザコン気質、生きる意味など、自身が抱える様々なコンプレックスと向き合うことになります。本作でクッツェーはブッカー賞を受賞しました。
●『恥辱』(1999年)
アパルトヘイト廃止後の南アフリカにおいて、時代の変動に翻弄される白人の教授とその娘の物語です。『マイケル・K』と同様、恥辱に耐えて生き抜こうとしている人間を描いています。主人公は、すべてのものを失い、救いを求めて暗中模索する中、なかなか(アパルトヘイト廃止後という)現実を受け入れることができません。人種間の軋轢や差別を取り上げた本作は、南アフリカのイメージを損なうものであると、発表当時は批判する声もありましたが、1999年にブッカー賞を受賞すると、その批判も少なくなりました。
7.カズオ・イシグロ
イシグロは長崎県で生まれ、5歳の時に家族とともに英国に移住した日系イギリス人の小説家です。主に一人称で書かれた彼の作品はどれも、人間の記憶や失敗をテーマとしています。日本を舞台にした初期の2作を除いて、日本を中心的なテーマとして扱っていません。しかし、本人は英国において日本人である両親の下で育ったことによって、周りとは「違う視点」を持つことができたと語っています。2017年にノーベル文学賞を受賞したことは、日本でも大きく報じられ、2018年には旭日重光章を受章しました。
●『日の名残り』(1989年)
第二次世界大戦後の英国を舞台に、経済復興や社会変化の中で衰退する階級貴族を題材とした物語です。かつて貴族に仕えていた主人公の執事は、過去の記憶をたどる中で、失われつつある上流階級の伝統的な文化や、自らの職業に対する倫理観を顧みます。イシグロは本作で1989年にブッカー賞を受賞しました。1993年には映画化され、アカデミー賞の複数の部門にもノミネイトされました。
●『わたしを離さないで』(2005年)
クライアントに求められた時に、自らの臓器を提供するために生まれた“提供者"と呼ばれる人々の世話をする介護人と、2人の提供者との三角関係を描いた、言ってみればSF映画です。主人公が、その現実を当たり前のこととしているかのような、その語り口からすると、一種のホラー映画とも言えます。それまでのイシグロの作品からすると意外な物語かもしれませんが、90年代に英国で羊を使ったクローン実験が、成功したことにインスパイアされて、この作品を書いたとイシグロ自身は語っています。また、先日世界を驚かせた、人間の受精卵の遺伝子を編集したというニューズのことを考えてみると、そう遠くない日にこのようなことが現実となりうるのかもしれません。(もう既にそうなっているのかもしれません。)
8.ブッカー賞
ブッカー賞は、英国の文学賞です。元々はイギリス連邦とアイルランド国籍の著者によって、英語で書かれた長編小説だけを対象として、その年に出版された最も優れた作品に与えられたものです。2014年からは、国籍にかかわらず、英語で執筆された長編小説全てを対象としています。2002年からは、運営がブッカー賞財団となっています。
9.サルマン・ラシュディ (インド/英国)
ラシュディの作品は、主にインドを舞台とし、魔術的リアリズムを用いて歴史に基づいたフィクションを描いています。その物語の特徴は、西洋と東洋の関係性を掘り下げることです。元イスラム教徒であるラシュディは、イスラムの開祖であるムハンマドの生涯を題材にした1988年の小説『悪魔の詩』で、ムスリム社会から激しい反発を招きました。当時のイラン最高指導者ホメイニは、ラシュディの死刑を宣告し、その後暗殺未遂事件が相次ぎました。この作品を日本語に翻訳した筑波大学助教授の五十嵐一は、1991年7月11日に筑波大学のつくばキャンパスの校内で何者かに刺殺されました。イラン関係者による犯行であったのではないかという推測が広まりましたが、真相は明らかになっていません。
●『真夜中の子供たち』(1980年)
英国からのインドの分離独立を背景に、インドで起こった様々な歴史的な出来事を著者が脚色をした寓話的大作です。ファンタジー的な要素を通して、独立後の転換期におけるインドが抱えていた様々な文化的、言語的、宗教的、そして政治的な齟齬をリアルに表現しています。1981年にブッカー賞を受賞し、ブッカー賞の25周年と40周年記念時にも賞を受賞しています。
10.マイケル・オンダーチェ (スリランカ/カナダ)
英国領時代のスリランカで生まれ、11歳の時に英国に移住し、その後カナダに移ったオンダーチェは、カナダを代表する小説家・詩人です。
●『イギリス人の患者』(1992年)
第二次世界大戦のイタリア戦線を舞台に、全身にやけど負ったイギリス人だと思われる患者と、カナダ人の看護師、シーク人の英陸軍工兵、そしてカナダ人のスパイの4人の物語です。題名の“患者"は、表面的には前述のイギリス人かもしれませんが、実際には4人とも、戦争という悪夢からの束の間の休息を取ろうとしている“患者"なのです。本作は1992年にブッカー賞を受賞しました。1996年には『イングリッシュ・ペイシェント』として映画化され、第69回アカデミー賞において作品賞、監督賞など、9部門を受賞しました。
11.ヤン・マーテル (カナダ)
私がマーテルの作品に親近感を覚えたのは、彼自身がフランス系カナダ人の外交官の子供としてスペインで生まれ、世界中を転々として育ち、大人になってからもインドやトルコなどを放浪し続けたという経歴もあるのかもしれません。読者を心身ともに物語の舞台へと導く、彼の独特な作風には賛否両論ありますが、一度は読む価値があります。
●『パイの物語』(2002年)
インド人の少年が、船でカナダに渡る途中に遭難し、同じ船に輸送されていたベンガルトラと共に227日間を海の上で過ごすファンタジー冒険小説です。難局に立ちながらも人間が力強く生きようとする姿を描いています。2002年にブッカー賞を受賞しました。2012年には映画化され、同作は第85回アカデミー賞で最優秀監督賞など4つの賞を受賞しました。小説は映画を超える傑作ですので、是非一度原作を読んでみて下さい。
12.エピローグ
日本にルーツを持つカズオ・イシグロ氏がノーベル文学賞を受賞したことは、同じく日本にルーツを持つ私としても、大変喜ばしく、感慨深いものでした。
一方、毎年ノーベル文学賞受賞が期待されている村上春樹氏については、受賞は難しいのではないかと、個人的には考えています。
その理由は、村上氏の作品には、“世界"はあるものの“世界観"がないからです。
ヨーロッパ人の視点から観ると、村上氏の“世界"は、子供が抱くファンタジーであり、ある意味“ハリー・ポッター"と同じジャンルなのです。
私の考える“世界観"とは、価値の対象や人生の意義について、はっきりと定義されるような概念を指します。
日本では、資本主義や民主主義といったイデオロギー(ある種の思想)を無反省に疑うことなく、真理として信じている人があまりに多すぎるのですが、ヨーロッパのインテリは、“自由や平等"といった“普遍的真理"といったことにさえ、疑問を持っています。
“自由や平等" “民主主義"を盲目的に信奉することは、“天皇を神とした戦前の軍国主義"を信奉することと同じ危険性を孕むことを忘れてはなりません。