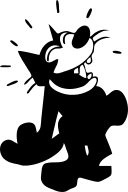1.プロローグ
今回は第二次世界大戦中のハリウッドの映画を取り上げます。1939年9月1日にドイツ軍がポーランドを侵攻したことをきっかけに欧州戦線が起こります。こうした状況に対して、ハリウッドも事態を慎重に見ながら中立を保っていました。1940年にドイツ軍がパリを占領し、英国への空襲を開始したことでアメリカ政府は危機感を強め、ハリウッドも戦争との向き合い方を模索しようとします。1941年12月に日本軍がハワイの真珠湾に攻撃し、日本と軍事同盟を結んでいた枢軸国のドイツとイタリアがアメリカに対して宣戦布告をすると、アメリカは連合軍として第二次世界大戦に参戦することとなります。
真珠湾攻撃を題材にした1970年のアメリカの戦争映画『トラ・トラ・トラ!』の有名なラスト・シーンでは、連合艦隊司令長官の山本五十六を演じる山村聰は、攻撃がすでに始まった後に宣戦布告がアメリカ政府に届くという手違いを残念に思い、次のように述べます。「アメリカの国民性からみて、これほど彼らを憤激させるものはあるまい。これでは、眠れる巨人を起こし、奮い立たせる結果を招いたも同然である。」(このことでアメリカは日本の攻撃を奇襲攻撃として、プロパガンダとして利用します。)
本当の山本も内心ではそう感じていたのかもしれませんが、彼が実際にこの台詞を発言したという証拠はなく、日本では一般的に言っていないとされています。アメリカでの生活経験のあった山本は、アメリカとの開戦には否定的でした。しかし、アメリカの高校生の多くは第二次世界大戦のことを勉強する中で「眠れる巨人」という表現を学びます。ハリウッドが生み出したこのフィクションは、アメリカ的な娯楽アクション映画を作ることで知られるマイケル・ベイ監督の『パール・ハーバー』(2001年)や“ハリウッドの破壊王"と呼ばれるローランド・エメリッヒ監督の『ミッドウェイ』(2019年)などの戦争映画でも描かれています。このことは「歴史は戦勝国が創る」ことの1つの現れであると同時に、映画というものがいかに大きな影響力を持つかの一例とも言えるでしょう。
真珠湾の奇襲攻撃を機にアメリカ国民の戦争参加の意欲が一気に盛り上がることとなりました。(実際には、アメリカ軍は日本軍の通信の暗号を解いており、宣戦布告がなされる前に日本軍が真珠湾を攻撃することを知っていました。ですので、真珠湾にそれまで停泊していた主力艦は沖合に逃がしていました。アメリカ政府は攻撃を事前に察知していながらも、攻撃をあえて許すことで国民感情を参戦へと向かわせるためのプロパガンダに利用しました。)とはいえ、日本とヨーロッパの2つの戦場での長い戦いに備えるためには、“巨人"にも身体と心の糧が必要でした。アメリカの軍隊と国民が士気と集中力を保ち続けられた背景には、ハリウッドの活躍がありました。
2.長編映画と共に上映された“ニューズ映画"
19世紀末に映像の技術が生まれた当初、製作されていた1本1本の映像は“サイレント"(無声)で、1分未満~数分程度のモノクロ映像でした。そのフォーマットから必然的に内容は物語性のあるものではなく、風景やイヴェントの様子をそのまま捉えたシンプルなものでした。そのため、映画という技術を発明したフランスのリュミエール兄弟の映画会社は、撮影技師を世界各国に派遣し、海外の様々な異国的な映像を記録動画として撮影しました。動画の内容や構成はいたってシンプルなものでしたが、これは後にドキュメンタリー映画へと発展していくこととなります。一方、米国のトーマス・エディソンの映画会社では、芸人などをストゥディオに呼び、パフォーマンスを披露してもらい、それを撮影しました。1894年には、エディソンはボクサー2人をストゥディオに呼び、史上初めてのスポーツ対戦の映像を収録しました。(ボクシングはサイズが限られたリングで行なわれるため、当時の技術には最適なスポーツでした。)こういった映画会社が映像作品を次々と公開していく中で、映画というメディアは徐々に報道媒体としての役割を持つようになっていきました。
記録動画を「ニューズ映画」(英語では“newsreel")に進化させたのが、フランスのビジネスマンのシャルル・パテとその兄弟でした。パテは新たな娯楽機器の登場に可能性を感じ、1896年にパリを拠点に蓄音機を販売する会社を設立しました。その後映画技術に着目し、1902年にはリュミエール兄弟から映画関係の特許を取得し、カメラの改善と製造に乗り出しました。同年にはロンドンに進出して工場と映画館網を広げていきました。1910年の時点ではヨーロッパ各地に加え、ニューヨーク、オーストラリア、そして日本にまでネットワークを広げ、ヨーロッパの映画用カメラと映写機の市場を支配するようになります。
パテは、1908年に「パテ=シュナル」というニューズ映画シリーズの製作をスタートさせ、フランスや英国の映画館でプログラムの一部として上映するようになりました。当時のものはもちろんサイレント(無声)で、一本が大体4分程の長さで、隔週でに新作がリリースされました。パテ社の映像の中でも特に有名なのが、オーストリアの発明家のフランツ・ライヒェルトの不慮の死を捉えたものです。ライヒェルトは現代のパラシュートと同じ原理を用いた発明品を披露するために、1912年2月4日にエッフェル塔のデッキ(高さ60m)から自ら飛び降りました。しかしその新しい発明品の外套は開かず、地上に激突し、死亡しました。
パテ社は、1912年よりアメリカの観客向けに「パテ・ウィークリー」を製作するようになりました。第一次世界大戦中には、従軍カメラマンが戦場で撮影した戦況報告映像をニューズ映画として上映し、大きな反響を呼びます。テレヴィがまだない時代において、ニューズ映画は動画でニューズを得ることができる唯一の手法でした。ニューズ映画を専門に上映する映画館も作られるほど人気の情報源となったのです。
パテ社の成功とニューズ映画の人気を受けて、パラマウント社は1927年より「パラマウント・ニュース」、フォックス社が1928年より「フォックス・ムービートーン・ニュース」、ユニバーサル社が1929年より「ユニバーサル・ニュースリール」を製作するようになります。一方で、パテ社のロンドン支部とアメリカ支部は1921年に分別し、アメリカ向けの「パテ・ウィークリー」は1931年から1947年の間はRKO、1947年から1956 年まではワーナー・ブラザーズによって配給されます。こうしたニューズ映画シリーズは各社とも50年代~60年代まで続けることとなります。
世界初のニューズ雑誌として知られる「タイム」を出版していたタイム社は、1週間のニューズをレイディオ・ドラマ化した30分のレイディオ番組「The March of Time」の放送を1931年にスタートさせます。この番組の人気をきっかけに雑誌の部数も大幅に伸びたと言われています。1935年よりタイム社は、同シリーズのニューズ映画版を製作するようになります。他のニューズ映画に比べて2倍の長さがあったこのシリーズは、インタヴュー映像や再現映像、主観的な視点を積極的に取り入れたことで、ドキュメンタリー映画の先駆けとなりました。映画会社の視点から製作されていた他のニューズ映画と違って、この「The March of Time」はジャーナリストの視点から製作されていたため、アメリカ的な進歩主義を掲げ、反ファシズム、反コミュニズムの視点が強調されていたことも注目すべきポイントです。
日本においては、1930年より松竹が定期的に製作し始めた「松竹ニュース」が一般的にはニューズ映画の始まりとされています。しかし、映画会社が主にニューズ映画を製作した欧米とは違って、日本では1934年ごろから、“トーキー"の発達に伴って新聞社が主体となってニューズ映画が製作されるようになりました。戦時中の1941年から1945年までは、国策宣伝のために情報統制がかけられていたため、陸軍省や海軍省の厳格な審査と検閲が行われていました。戦後も再び新聞社が主体となってニューズ映画が作られますが、テレヴィ放送の開始と一般家庭への普及によってニューズ映画は急速に衰退へと向かうこととなります。とはいえ、アメリカでは60年代ごろには完全に姿を消したのに対して、日本のニューズ映画シリーズの中には90年代まで製作が続けられたものがいくつもあります。
こういったニューズ映画は、第二次世界大戦中、アメリカに限らず、日本やヨーロッパ各地でもプロパガンダ的な役割を果たすようになっていくこととなりました。
3.子供から大人まで魅了した“カートゥーン"
ニューズ映画や短編映画とともに長編映画の前に上映されていたのが、短編アニメイション、いわゆる“カートゥーン"でした。
アニメイションの歴史は、映画が生まれた1890年代より半世紀も前に生まれました。1830年代には“おどろき盤"という名称で日本では知られる装置が開発されました。円板のような回転体に“コマ"に相当する絵が順番に描かれ、それを高速に回転させることで動いているかのようにみせる仕組みです。その少し後にのぞき穴を通して見る「回転のぞき絵」やいわゆる「パラパラ漫画」が生まれたとされています。1868年に英国の発明家のジョン・バーンズ・リネットは「キネオグラフ」という名前でパラパラ漫画の特許を取得しました。「キネオグラフ」は直訳すると「動く絵」という意味です。
映画技術が誕生したばかりの19世紀末には、そのリアルな映像が最大の魅力でした。そのため、いわゆる手書きアニメが誕生するのは、サイレント映画が一般的に普及した後である1910年前後です。1910年代になって、アメリカのアニメイション映画は産業として形成されるようになります。1919年に、オーストラリア出身でニューヨークを拠点としていた映画プロデューサーのパット・サリヴァンとアメリカ出身のアニメイターのオット・メスマーは、パラマウント映画のために黒猫のキャラクターを主人公にした白黒の短編サイレント・アニメイション・シリーズを製作しました。大きな目と2本脚で歩く特徴的なそのキャラクターには「フィリックス・ザ・キャット」という名前が付けられ、アメリカでは子供から大人まで広く人気を博すようになりました。アニメ史上初のスター・キャラとなったフィリックスは、日本でも「フェリックス」という名前で親しまれ、現在に至って高い人気を誇っています。
映画業界がサイレント映画の時代から“トーキー"へシフトする中で、頭角を現したのが米国のディズニー社です。ディズニーは1928年に短編アニメイション作品『蒸気船ウィリー』で「ミッキー・マウス」と「ミニー・マウス」というキャラクターを“デビュー"させ、高い人気を得るようになります。ディズニーは1932年には「グーフィー」、1934年には「ドナルド・ダック」と、その後も人気キャラクターを次々と登場させていきます。
子供っぽくて清潔なイメージのディズニーのキャラクターに対して、パラマウント社は“大人志向"のキャラクターを生み出します。その代表例が1930年に初登場した「ベティ・ブープ」です。狂騒の20代を経てアメリカ社会における女性の立場が大きく変わっていたことを受けて、ベディ・ブープは当時の“新しい"スタイルの女性であったいわゆる“フラッパー"をモデルとして、セックス・シンボル的なキャラクターとして描かれました。しかし、30年代半ばになると、ヘイズ・コードの導入によって露わな性的魅力はトーン・ダウンされることとなります。その一方で人気を博すようになったのが、船乗り(水兵)の「ポパイ」でした。1929年にコミック・ストリップ(新聞の連載漫画)のキャラクターとして生まれたポパイは、1933年ごろから短編アニメイションに登場するようになります。
ワーナー・ブラザーズは、1930年ごろから「ルーニー・テューンズ」のカートゥーンを製作するようになり、次々と“ルーニー"(狂った)キャラクターを生み出していきました。中でも1935年に短編映画『ポーキーの母親参観』で初登場した吃音の豚「ポーキー・ピッグ」はワーナー・ブラザーズの花形スターとなります。1937年の『Porky’s Duck Hunt』では変化球的なキャラクターとして「ダフィー・ダック」が初登場し、1940年の『野生のバニー』ではブルックリン訛りで大胆不敵の「バッグス・バニー」が初登場します。こうしたキャラクターによってルーニー・テューンズは高い人気を得るようになります。
また、MGMは、一足遅れて1940年よりウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラの2人のアニメイターによって、体が大きくて凶暴だがどこか憎めないところのあるネコと頭脳明晰なネズミのドタバタ劇を製作しました。その作品の成功を受けて、猫とネズミの新しい名前が募集されました。そして猫には「トム」、ネズミには「ジェリー」という名前が付けられました。本シリーズは日本を含め世界中で大人気となり、アカデミー賞の受賞本数ではミッキー・マウスやルーニー・テューンズを凌ぐほどのヒットでした。
1941年にアメリカが第二次世界大戦に参戦すると、こういったアニメイション・キャラクターも“徴兵"されました。真珠湾攻撃の翌日、アメリカ政府は戦時体制への協力を国内産業に求めます。アメリカ軍はディズニー社が南カリフォルニアのバーバンクに構えていた本社に立ち入り、近くにあったロッキード社の工場を守るための拠点としました。ディズニーは、その後軍隊向けの教育・訓練動画や一般向けのプロパガンダ映画を多く製作するようになりました。一方でポパイはそのキャラクター柄から海兵隊の一員となり、ナチスや日本海軍と戦う様子を描いた短編アニメイションが製作されました。
また、ディズニーを始め、各映画ストゥディオの人気キャラクターは軍隊のエンブレムに用いられ、兵隊の団結力と士気を高める一躍を担ったとされています。アニメ・キャラがこのように使われたのは、第二次世界大戦で始まったことではありません。1920年代終盤にアメリカ海軍の爆撃飛行隊は、導火線に火がつけられた爆弾を抱えるフィリックスをマスコットとして使用するようになりました。このエンブレムは今でも使用されています。
4.ハリウッドが参戦するまで
1930年代後半のハリウッドが製作していた長編映画のほとんどは、ヨーロッパとアジアで繰り広げられる戦争にそもそも触れないか、あるいはそれを他人事のように婉曲に扱ったような作品ばかりでした。しかしこの世界大戦の影響がアメリカにも及ぶようになると、戦争を題材に扱った劇映画が次々と製作されるようになり、やがてプロパガンダ的ドキュメンタリー映画も数多く製作されるようになりました。
そもそも“戦争映画"はハリウッドの初期から人気のジャンルで、そのテーマからしてドラマに富んでいることから、興行成績のみならず高い評価を受けた作品が多く製作されてきました。第1回アカデミー賞で作品賞をとったのも、第一次世界大戦を題材にし、空中戦を美化した『つばさ』(1927年)です。
こうした作品に対して、当初から感情を高まらせ、脳を刺激するようなハリウッドの映画の製作方法に対して懸念を抱く人たちは少なくありませんでした。サイレント映画が普及し始めた頃から、アメリカの宗教団体などは「映画というものは、国民の行動や価値観に大きく影響し、 道徳の低下に繋がる危険性がある」と訴えていました。そういった心配を和らげるために、ハリウッドは1930年代にヘイズ・コードを導入し、自主規制をするようになりました。20世紀後半には「テレヴィが若者の脳を腐らせている」、21世紀に入ってからは「インターネットやSNSが若者をダメにしている」と言われることが多いですが、新しいメディアに対する不安は、いつの時代にもあるようです。
アメリカが本格的に第二次世界大戦に参戦する前の数年間、ハリウッドは映画の製作に対してかなり慎重になっていました。30年代における"トーキー"の普及によって、映画鑑賞はアメリカ人のライフスタイルの一部となり、国民の大人の半数以上が最低週に1度は映画館へ足を運んでいました。ハリウッド映画はアメリカ人の倫理観を腐敗させていると思われていたように、ハリウッドが映画を製作することによって「アメリカはこの戦争に参戦すべき」という国民感情が助長されるのではないかと懸念していました。
しかし、映画会社の経営者の多くはユダヤ人であり、著名映画監督の中にはフランク・キャプラやウィリアム・ワイラーのようにヨーロッパ移民もいたことから、ヒトラー率いるナチスがヨーロッパ各地を襲撃し勢力を拡大する中、いてもたってもいられないような思いだったのでしょう。とはいえ、ハリウッドの映画会社の経営という観点からすると、ヨーロッパ市場を失いたくないという思いもあり、できるなら戦争に巻き込まれず、中立でいたいという願望もありました。
しかし、1940年中頃までにはドイツ軍は、フランス、ベルギー、オランダそれにノルウェーを占領し、英国に対して空襲を始めるようになります。1941年6月には、ナチス・ドイツは独ソ不可侵条約を一方的に破棄してソ連に侵入し、独ソ戦が勃発しました。ヨーロッパで事態が深刻化する中、ハリウッド映画は戦争と向き合わざるを得ない立場に置かれます。『赤ちゃん教育』などの映画で知られていたハワード・ホークス監督は、1941年に第一次世界大戦中に実在した人物を題材にした『ヨーク軍曹』を製作し、同年の映画作品の中でも全米興行収入1位に輝きました。前述のワイラー監督は、第二次世界大戦初期の英国の田舎町の家族の日常を描いた『ミニヴァー夫人』を製作し、ドイツと戦うヨーロッパの国々がアメリカの支援を必要としていることを訴えました。本作の製作の途中に真珠湾攻撃が起こりました。もうじっとしていられないキャプラはアメリカの首都・ワシントンDCに向かい、アメリカ軍の若い兵隊と国民に向けてこの戦争への参戦の必要性を伝えるための映画作りに取り掛かります。